
こんにちは。
全方位型コーチカウンセラー/公認心理師の佐藤真紀(さとう まき)と申します。
皆さまを、最悪の悩みから「自分史上最高の姿」へと導かせていただきます。
ここで私がカウンセリングルーム「相談室09(ゼロキュウ)」を運営するに至った経緯をお話させてください。
時は、幼少期までさかのぼります。
周囲の大人の顔色を伺い、場を和ますためにふざけ続けた幼少期。
元気な自分を演じながら、内向的な部分も多く持つ私は、人前では絶えず緊張状態にあったと思います。たとえそれが家族でも。
子供の頃から漠然とした生きづらさを感じながら、人間関係の中で憤りや葛藤を抱えることも少なくありませんでした。
その葛藤を振り払おうと、自分勝手な生き方をしていた時期もありました。

そんな私が心惹かれたのは、人間の心理。
人々の生き様と生きていく上で抱えておられる心境のリアルな姿でした。
自分の内面の葛藤と戦っていた私にとって、人間の心理に強く惹かれたは必然だったのかもしれません。
そうして、精神科医療機関の相談室で仕事をはじめた傍ら、市町村や県の主催する市民の方向けのメンタルヘルス相談員や講師として、また依存症指定相談員として、医療観察法参与員として、これまで10代~90代まで様々な年齢層や職業の方々に、約22年間2万件以上のカウンセリングを行ってきました。
その中で私は自らも生きづらさを感じながら、より本質的な心理スキルやコーチングを系統的に学びました。
その後「もっと広く、生きづらさを抱えた方のお悩みに寄り添うことはできないだろうか」という思いが強くなり、私は22年間の会社員人生に終止符を打ち独立しました。

そのような経過を経て、私はカウンセリングルーム「相談室09(ゼロキュウ)」を開設するに至りました。
安心してどんな内容でもお話していただけるように、また、皆さまが「自分史上最高の自分」と出会うために、皆さまのお悩みの内容に沿った形でオーダーメイドのカウンセリングを提供しています。
これまで10~90代と幅広い年齢層や職業の方々約2万件の心理相談に携わった実績のもと、心理面のみならず、身体症状や環境までをも考慮し、正確なカウンセリングによる最速の問題解消に導きます。

カウンセラーやライフコーチは、環境を変える力、社会を変える力を持っていると信じています。
しかし、それは相談者ご本人が持つ、自身の自分を信じる力があってこそです。
クライアントが救われると、その家族や周りに人達もポジティブな方向に向かっていきます。
クライアントの変化により、クライアントを取りまく生活自体が豊かになるのです。
たった一人の意識が変わることで、職場環境や家庭環境、人間関係を変えることも可能なのです。

そうなるために「どうせ変わらない」を「でも、変わりたい」という気持ちが土台となってくるわけです。
あなたはもう十分考え、試行錯誤してきたと思います。
毎日が戦いだったのではないでしょうか?
自分の気持ちを言葉にしたこともなかったかもしれません。
自分の気持ちを少しずつでも言葉にできれば、それまで感じていた生きづらさの原因がひも解かれ、人生に希望を持てるようになります。
ご自分では気づいておられない、心の中に抑圧された感情も一緒に共有する「全方位型カウンセリング」
そして、これまでの最悪な悩みを最高の悩みに変換し、その解消を通して心地良い生活を実現していく。
あなたのお悩みの解消と今後のキラキラと輝く未来に向け、私は全力で伴走させて頂きます。
LINEお友だち追加からのご予約がお得です。
【もう少し詳しいプロフィール】
↓ ↓ ↓
あなたのこれからの人生が心地良いものになるために、全対応型カウンセラーである私の考え方を少しでも理解、共感して頂ければありがたいと思います。
そもそもなぜ、私がカウンセラーという職業に就いたのか、挫折や苦境からどのように抜け出したのか、もう少し詳しくお伝えいたします。
少々長くなりますが、興味のある方はぜひ読んでみてください。
親の機嫌の変化が不安で、テストの点数を良くしようとし続けた幼少期

子供の頃の私は、幼稚園の頃から机の前に座って勉強をすることを習慣づけられていた。
幼稚園の頃の勉強時間は朝9時から。日記を書いたり、図鑑を読んだり。
小学校に入学するにつれ、学習内容は日記から勉強に変わっていったし、机の前に座る時間帯も幼稚園の頃とは違って増えていった。
好きなテレビ番組を観ることはできず、残念に思っていたがそういうものだと思っていた。。
頭の中ではいつも親の陰影が付きまとい、友達と遊びながらも「〇時には帰って勉強しなくちゃいけない」などと考えていた。

もちろん学校の定期テストでは「良い点数を取らきゃ」と勉強を頑張ったし、良い点を取って家族に褒められる事が、自分でもどことなく誇らしかったことも覚えている。
この頃は、テストで良い点を取れば親に認めて貰えると思っていた。
勉強はあまり好きではなかったけど、親の機嫌を損ねない為にも必死で勉強をした。
一方で「テストで良い点数を取らなければいけない」という苦しさはあった。
親は満点を取らなくても怒りはしなかったが、その表情からは笑顔が消えた。
その度に私は親に「悪いことをした」という気持ちになった。
だから、親のためにも自分のためにもテストで良い点は取らなければならなかった。

勉強だけではなく、他のどんな事であれ、家族の中に不穏な空気が漂うのが嫌だった。
家族の中に漂う不穏は、全部自分のせいだと思っていた。
私は家族みんなの表情や家族内の空気に絶えず気を張り巡らし、アンテナを張っていた。
正義をかざしながら、冷酷さもあった自己の不一致
小学生の頃は活発な子供だったと思う。
私や私の友達をからかう男子などいようものなら、平手打ちだった。
相手の鼓膜を破ったこともある。
また、同級生に虫を投げてその子が驚くのを喜んでみたり。
情が厚い部分と冷酷な部分が混在する子供だった。

だけど振り返れば、からかう男子をやっつけている場合ではなかった。
私がやっつけられても良いような行いを、私自身がしてきていたのだ。
それは今だから気づけることだ。
中学校でのいじめと「助けて」を言えずに、毎日緊張して過ごした日々

そして迎えた中学生活。
何の不安もなく中学校に進学した。
相変わらず勉強も運動も頑張っていたし、テストで良い点を取るのが私の義務だと思っていた。
100点満点のうち98点でも悔しかったし、満点じゃないことが気持ち悪かった。
80点台を取ろうものなら、自分が悔しいというよりも、親にこの点数をどう伝えようと心配になった。

ある日ふと、学校のクラスの空気がこれまでと微妙に違う事に気づいた。
どうもクラスの一部が私を避けているような気がした。
気のせいかとも思ったが、…違う。
確実に私を避けていた。
彼らはクラスの中でも目立つ集団。
話す声も振る舞いも大きく、どうしても意識がそっちに向いてしまう。
気にしないように、気にしないように、なるべく平静を装っていたが、教室内を歩けば距離を取られ、廊下を歩けば、私から離れるように両脇に寄られる。

「気のせいかも」と何度も言い聞かせていく中で、日々同じような場面に遭遇し、でもその状況が分からないまま時間が過ぎていった。
…私、イジメに遭っている?
そうであって欲しくないというほんの僅かな期待は、日を追うごとに打ち砕かれていった。

自分の置かれた状況を認識したとき、私は呆然とした。
同時に、イジメられている自分をとても恥ずかしく思えた。
だけど、当時の自分にはどうすることもできなかった。
学校の先生には相談できなかったし、相談することが恥ずかしかった。
そのことを誰かに相談することに対し、自分のプライドのようなものが邪魔をした。
もちろん家族にも相談はできなかった。

「イジメられるような子で、ごめんなさい」
家族に申し訳ない気持ちでいっぱいだったのを覚えている。
毎日、平静を装って何でもないふりをして、過ごした。
学校では休み時間が怖かったし、家では夕食の時間が怖かった。
自分の変化を周りの人に知られる事が、怖かった。

だけど、そうそうごまかし続けられるわけがない。
沈んだ気持ちは顔に出ていただろうし、家での夕食の時間には自然と涙がこぼれた。
当然、家族からは学校で何かあったのか聞かれるはめになったが、やっぱりその理由は言い出せなかった。
「何でもない」と答えながら、「ごめんなさい」と心の中で繰り返した。

その時の記憶は曖昧で、何がきっかけだったのかは思い出せないが、たぶん隠しきれなかったんだと思う。
結局親にイジメのことを告白し、そこからは何があったんだっけ…芋づる式に学校の先生にも話さざるを得なくなり、でもどこかホッとしてはいた。
「イジメが解決するかもしれない」という思いからではなく、周りに嘘をつき続けなきゃいけない苦しさから解放される安堵感からだと思う。
「何かあったの?」と聞かれ「別に何もない」と答え続けるには、限界があった。
夜は、明日の学校が心配でなかなか眠れなかったし、朝は、誰かが新聞を配る自転車の音で目が覚めた。
ちょっとした物音で目が覚めるのだ。
そしてその日、これから登校しなきゃいけない事を考えて怖くなる。
そんな毎日だった。

結局、担任の先生が介入する形で、イジメていた子たちは自宅まで謝りに来てくれたけれど、その時にホッとした気持ちがあったかは覚えていない。
その後も楽しい学校生活に戻れたかと言ったら、そうでもないような感じだったと思う。
中学校の後半…もう記憶自体が曖昧だ。
ただ、親への申し訳なさはその後もずっと続いた。
高校入学/体罰交じりの授業と同級生の死、記憶の喪失

そんな中学校生活の中、目標とされていた高校には入学できた。
親からの指定でその高校しか選択肢はなかったし、そこに入学しなければいけなかった。
だけど、結果を出せた自分が誇らしくもあった。

入学してみると課題は満載でテストも多く、入学早々目の前が真っ暗になった事を覚えている。
想像していた楽しげな高校生活とは全く違い、過酷な毎日だった。
やるしかないから、泣きながら課題に取り組んだ。
高校に入学すれば、毎日の勉強や受験勉強から解放され、それまで苦しかったもの全部から解放されるような気になっていた。
でも現実には、泣く泣く膨大な課題に取り組んでいる自分がいた。
今考えれば、全て自分の思い違いだった。

高校で、新たな友人もできた。
だけど、いくら思い出そうとしても高校の記憶は断片的で、3年間どんな風に過ごしてきたか、見事に忘れてしまっているのだ。
自分が何組だったかとか、担任の先生が誰だったかとか、どんな授業内容でどんな出来事があったかとか、その他色々な事が思い出せないのだ。
とにかく、詰め込み式の勉強に追われ、数々のテストに追われ、その勉強についていくために、部活動には参加しなかった。
文武両道を掲げる校風の中、みんなどうやって色々な事をやりくりしているのか不思議だった。
まして、人の事を考えている余裕なんてなかった。

自分の目の前の課題をやっつけていくだけで、その日その日が終わっていった。
自分が将来何をしたいのか、どうなりたいのかなんて、考える機会もゆとりもなかった。
勉強が嫌いなわけじゃなかった。
興味のある分野は知りたかった。
一方で、興味のない分野は全く頭に入らなかった。
だけど、平均的にバランス良く勉強しなくちゃいけない。
そうしなければ、努力の結果はテストの点数として公表されるし、当時は上位30人までの氏名が、廊下に張り出された。
もしそこに入らなければ親に申し訳ない。高校でもそんなことを思っていた。

竹刀を持った先生が見回る教室の中、とにかく必死で教科書や参考書に向かい続けた。
受験の前には、下級生に見送られる形で全校壮行式というものがあったことは覚えている。
そこで、ほら貝を吹きながら応援の言葉かを叫んでいる先生もいた。
今考えると、滑稽だ。
だけど当時の自分は何かを考える余裕もなく、毎日必死だった。
2年の夏休みに、同級生が死んだ。
生徒の間では「自殺したんだ」という話が広がっていったが、真相は分からない。
過去に自殺した先輩も何人かいたし、自殺者が出たとしてもあまり違和感はなかった。

そのうち、私にも異変が起きた。
勉強している時に、顔を引っ搔くようになったのだ。
痛かったかどうかは、覚えていない。
だけど顔を引っ掻いていたその感覚は、いまだに覚えている。
引っ搔いて、治りかけの傷をまた引っ掻く。
かさぶたができては、それをはがす。
傷だらけの私の顔を見て、親は手袋の着用を勧めたけど、それじゃ勉強に集中できない。
止めようと思っても、引っ掻かずにはいられなかった。
当時の写真を見ると、私の顔は傷だらけだ。

3年に進学した後、私のキャパシティは限界を超えた。
それまで知らず知らずのうちに溜まってきていたプレッシャーのようなものが、容量を超えてはじけ飛んだのかもしれない。
勉強に身が入らなくなり、夜遅く帰ることもたびたびあった。
親に「勉強してきた」と嘘を言うには、遅すぎる時間。
親へ反発しながら、でも心の中で罪悪感を感じながらも、それでも学校には登校し続けた。
遅刻することはあっても、かろうじて学校には行き続けた。

大学の志望校は、東京の私立大学を選んだ。
名の知れた大学であれば、親も納得するはず。
そんな気持ちもどこかにあった。
それで進路担当の先生に希望を伝え、推薦が決まった。
要は、体の良い形で受験勉強から逃げたのだ。
逃げるように東京へ。多様な価値観に癒され始めた日
東京の大学に進学し、親元を離れた。
いざ親元を離れる時はどこか不安でさみしかったが、実家を離れるワクワク感があった。
自分の好きなように何でも決められるし、自分の好きなようにできると思った。

大学には行っていたが、それまでの鬱憤を晴らすかのように遊び回った。
私立は学費が高く、その分奨学金を貰って大学の授業には出席していたが、授業はそんなに面白くなかった。
だけど、さまざまな人と接していく中で、人には色々な価値観があり色々な考え方があり、どれが正解でどれが間違いなんてこともない、ということを知った。
驚きの連続だった。
人々の価値観は本当に多様で、今まで自分がどんなに狭い視野で生きてきたかを知った。
毎日が新鮮で、楽しかった。
だけど実家の事を考えると、自分が楽しんでいることが悪いことのように思えた。
その思いを払拭すかのように、その場その場の楽しさを求めた。
自分のやりたいようにするためには、他人を傷つけても平気だった。
「お互いさま」という言い訳のもと、当時の私は好き勝手やっていた。

そんな私が興味を持った大学の講義があった。
「犯罪心理学」
それは刑事政策の授業の中で扱われたものだったが、私は人間の内面に潜む光と闇に強く関心を持った。
私は心理分野に夢中になり、犯罪心理を専門とした教授のゼミに入り、それからは毎日人間の光と闇、正常と異常とに夢中になった。

「何が正常で、何が正常でないのか」その境目は誰がどうやって線引きするのか…追及しながら教授や学生同士で討論を重ね、刑務所へも足を運び、そこに収監されている方々と面会した。
裁判の傍聴に通っては、加害者と被害者、両者の心理的情景をくみ取ろうと必死になった。
また、世間ではマイノリティとされている方々とお会いして、色々なお話を聞いた。

毎日どんな思いでその人たちが過ごしているのか、どんな葛藤を持っているのか…そこには数々の葛藤や苦悩、生き様があった。
当時「社会不適合」というレッテルを貼られてしまった方々と接しているうちに、私自身が癒されていくような気持ちになったことを覚えている。

皆、さまざまな事情や思いを抱えながら、一人一人の人生のドラマを必死で生きていた。
そんな中、就職活動が始まったが「このまま東京に残りたい」という私の希望は父に一蹴された。
自分の希望を貫き通すほどの強さがなかった私は、結局地元に戻った。
地元には戻ったが、実家には戻らずに独り暮らしを始めた。
それが当時、精一杯に張った、私の心の砦だった。
就職し、自分と向き合い始めて感じた違和感
地元の出版社に就職し、私は記者職として配属された。

取材を通して、色々な方からさまざまなお話を聞くこととなった。
そこにはやっぱりそれぞれの生き様があり、色々な思いがあった。
一方、仕事は深夜まで続く事はざらにあったし、休暇はあるようでないようなものだった。

上司からもたくさん指導を受けた。
上司に怒られる時には「ねぇ、あなたは今、私に怒られてるんだよ!?」と肩を揺すられたが、私は私なりに反省しているし、そう言われてもどうしようもなかった。
だけど傍から見ると、私は反省しているように見えないようなのだ。
”ナポリタン”を”ナリポタン”と書いて、誰もその間違いに気づかないまま雑誌記事として発売されてしまったこともある。
当然問題になり、記事を書いた当事者として反省はしたが、心の中で「誰も気づかなかったなら、私だけの責任じゃない」なんてことも考えたりしていた。
今考えると、私は根本の部分で反省していなかったのだと思う。
反省していると当時の自分は思ってはいたが、どこかで何かしらの言い訳を探していたのだ。
間違っている個所を指摘されても指摘されても正せないまま、始末書は人一倍書いたと思う。

でも仕事自体は好きだったし、何より色々な方々から興味深い話を聞けることが、魅力だった。
だけどそのうち、心身ともにしんどくなった。
ネタを探し、取材をして、記事を書く。その繰り返しが苦しくなった。
そのうち、取材で人に会うのも面倒になった。
そんな状態で取材を続けることは、相手にも失礼だ。
それにそんな状態で良い記事なんて書けるわけがない。
だけど何より、取材を通じて垣間見えた人々の生き様を通じて、私はもう一度人間の心理についてより深く知りたくなったのだ。

…私は悩み、もう一度心理の分野に身を置く事を決めた。
その後職場を退職し上京。
そして私はまた学生に戻った。
東京で昼間はアルバイトをしながら、夜は学校に通う日々が始まった。
多忙な毎日で体はしんどかったが、また生き返ったような気がした。
精神科医療機関への転職。血を吐く思いで働いた末の退職勧告と自暴自棄の日々

就職と2度の学生生活。
紆余曲折ありながらも私は24歳になっていた。
地元に再び戻り、精神科医療機関へ入職することとなった。
再スタートを切った私は希望と使命感を胸に、日々の相談業務に向かった。
実際に仕事をしていく中で、地域にこんなにもメンタル面での悩みを抱えている方がいるということや、メンタル問題に伴う生活不安、時には警察が介入するようなトラブルも含めて多種多様な多くの相談があることに驚いた。
どこまで自分が関われば良いのか、当時の私は探り探り必死で考えた。
一度その方の相談に携わるということは、つまりその方のこれからの一生に寄り添っていくということだ。
「その方の骨まで拾うことは、できないのよ」と、当時の上司に言われた事を思い出しながら、それでも自分に何かできることはないか、相談に来られた方々と一緒に模索し、考え続けた。

1日の業務が終わると、それはもう毎日ぐったりだった。
帰宅後、部屋の電気を点ける気力さえなく、気づいたら真っ暗になっていた、なんてことは日常茶飯事だった。
当時の私には、相談業務を受ける際に重要となってくる「心の境界線」がなかったのだと思う。
「心の境界線」とは、自分の課題と他人の課題を分けて考えること。
他人の心の敷地内に、自分の心の敷地が被っていないか。
被っていたら、自分事と他人事を混同しがちになってしまう。
だから、当時の私は相談者の相談内容を聞きながら、まるで自分の事のように頭に来たり、悲しくなったり、辛くなったりした。

その人の相談内容を、その人に代わって私が解決しなければいけないような気になっていた。
今振り返ると、当時の私は自分と他者との境界線が曖昧だった。
仕事熱心という見方もできるだろうが、結局はその方の問題や課題を、私がが肩代わりしていたようなものだ。
時には、相談者の家族が来院された際に話し合いが平行線となり、激高した家族に殴られたこともある。
それでもご本人の希望を通さねばいけないと、殴られながらも私は姿勢を崩さず家族を睨みつけた。

そんな風になってしまう私のやり方は、本当の支援とは言えなかった。
話し合いの最中に、ご本人の関係者に罵倒され、捨て台詞を吐かれ、拳をあげられたことは、1度や2度ではない。
私は「ご本人の希望の実現」を盾に、要は自分の思うやり方を貫くために、周囲の方々と喧嘩していたようなものかもしれない。
目まぐるしく過ぎていく日々の中で、あっという間に10年が過ぎた。
その間、公私ともに色々な出来事があった。
恋愛も重ねたが、私の欠陥部分がいつも邪魔をした。
親しくなると、相手を突き放す。
いつもその繰り返しだった。

器用でない私は、プライベートの時間まで仕事での葛藤や思いを引きずることが多かった。
当時はそれほどストレス等は意識していなかったが、日々蓄積された消耗感は私の隅々に不具合を起こしていたのかもしれない。
不眠になったり、強い焦燥感や不安に悩まされた事もあった。「自分はうまくやれていないんじゃないか」そんな心配が頭をよぎることもたびたびあった。
日々自分を奮い立たせ、自分の欠陥を埋めていくかのように、通常業務に加えて外部の委託業務を次々と受けていった。
公的機関からの市民の方向けへの相談業務、大学の兼任講師、実習生の認定指導者、医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)の精神保健福祉参与員等、行政や民間企業での講演…過ぎ行く年月の中で、私はがむしゃらに働いた。
そして勤務先では医療相談室長となった。

仕事の幅が広がりやりがいも感じる反面、いつも疲労感は拭えなかった。
特に感じていたのは、精神的な疲労感。
そして「周りの要望や期待に応えなければいけない」という切迫した思い。
ストレスフルな毎日、そしてそのストレスを自らうまく対処できていない状態のまま、他の人にはストレスとの付き合い方を説いていた。
私は、偽物だった。

精神科の医療機関に勤務し、15年になろうとしていた。
勤続年数が長くなるにつれ、地域の同じ業界の中ではある程度、名前と顔を知られるようにもなっていた。
そんな中、その日は突然やってきた。
ある日の夕方、当時の職場の上司に呼ばれた。
要件を聞いたが「応接室まで来れますか?」その一言だった。
応接室に入ると、そこには上司2人が座っていた。
状況を呑み込めないまま座った私に、日頃の私の業務姿勢に対する注意喚起と今後の自分の進退についての考えを問われた。

それまで職場で培ってきたもの全てが壊れるのを感じた。
本当はずっと前から壊れていたのだろうが、私は職場でうまくやれていると思っていた。
正確に言えば、うまくやれている自分を演じることができていたと思っていた。
でも、そうではなかった。
その状況に、自分自身が全く気付いていなかった。
それまで届いていた私の声は、もう届かなかった。
説明のしようもなかった。

直面しないように、直視しないようにして放置してきた私の欠陥部分。
自分の欠点を直視せず、他のことで自己を補おうとしてきた自分。
そんな私が招いた、起こるべくして起こった状況だったのかもしれない。
私は退職の道を選び、しばらくただ呆然として過ごした。
自分のすべてが否定された感じがした。
心の中は、悲しさ、怒り、寂しさ、悔しさ、後悔…色んな感情がぐちゃぐちゃに渦巻く一方で、完全に自分自身を放棄したような状態で過ごした。

セルフネグレクト。
完全にその状態だった。
何もする気が起きず、自分が存在する意味が分からない状態で過ごした。
道を歩く盲導犬を見ては「犬でさえ自分の役割を果たしているのに、自分にはその役割すら無い」と泣けてきた。
当時、一緒に暮らしていた犬だけが支えだった。
完全に私は人間不信になっていた。
そしてそんな私に犬はただ、ずっと寄り添ってくれた。
その犬は今はもう亡くなってしまったけれど、彼が私を見つめて続けてくれたあの優しくまっすぐな目を、私は一生忘れない。

個人的に契約していた委託業務は、職場の退職後も続けていた。
でも、それらの収入合わせたとしても生活費としては足りず、生活は維持できない。
そしてどんな時も傍にいてくれる飼い犬に、申し訳ない思いでいっぱいになった。
そんな気持ちも手伝って、私は動き始めた。
腐ってても仕方ない。
自分の頭だけでぐるぐると考えて、人間不信が治るわけでもない。
自分に欠陥があるなら、それをまず見直そう。そう思った。
ちょうどその時に募集を開始していたアンガーマネジメントの講習を受けに東京へ飛んだ。

アンガーメントファシリテーター養成の約15万円の講座。
その時の私には大きな額だったが、日本アンガーマネジメント協会の集中講義を受けた。
体当たりで、自分の嫌な部分をさらけ出し、他の参加メンバーの協力を得ながら、3日間の集中講義を終えた。
この時をきっかけにして、怒りの感情には構造があり、取扱い方があることを学んだ。
怒ること自体が悪いのではなく、怒りを感じた時に相手に正しく伝える事が大事なのだと知った。
そして学んだことをこれからの生活に活かしていこう。
そう心に決めた。
再起をかけた新たな出発。変わらなかった負の感情

その後私は心機一転、別の精神科医療機関へ入職した。
相談室の相談員として、受診希望の方のカウンセリングやメンタル的なお困りごとの相談を受けるのが主な仕事だった。
相談対応する疾患の幅広さに改めて社会のひずみを感じながらも、精神的な問題への理解や先進的な治療方法や受診までのマネジメント手法を、日々の業務の中で学んでいった。

そんな中、私は私で本格的に自分と向き合い始めた。
生きづらさを抱えながらの人生を、何とかこのまま逃げ切ろうとしていた自分に気づいたのだ。
ここにきてもなお私は、色々なものを犠牲にし、人との繋がりも大切にできなかった。
うまくやろうとしても、空回ることが多かった。
これまで無視してきた私の心が、限界を迎えていた。
実際、このまま生きていくのは難しいかもしれないとも思った。
そんな時間をこの先も歩んでいくのかと思うと、全く先が見えなかった。
もう、自分と向き合うしかなかった。
苦しかった。
私は、初めて自分の心と正しい方法で向き合い、しっかりと自分の中の本当の自分に耳を傾けた。
見ないようにしてきた自分の欠陥部分も含めて、ありのままの自分と向き合った。

そうして少しずつ気づき始めた、自分の心。
そこから少しずつ、自分自身を直視することができるようになった。
私は、苦しかったのだ。
本当は、助けて欲しかったのだ。
自分の感情に気づいた私は、心理療法の力を借りて自分の感情を取り扱う術を学んだ。
そしてそれを日常生活で繰り返しアウトプットし、対人関係のスキルを習得しようと、私は懸命になった。
自分の中の本音の自分を受け入れる事ができた瞬間、初めて自分時間が動き始めた事を覚えている。

今、私は私として生きている
幼少期から、自分がどこに向かっているのか分からず、ただがむしゃらに人生を逃げ切ろうとしていた私は、今はもういない。
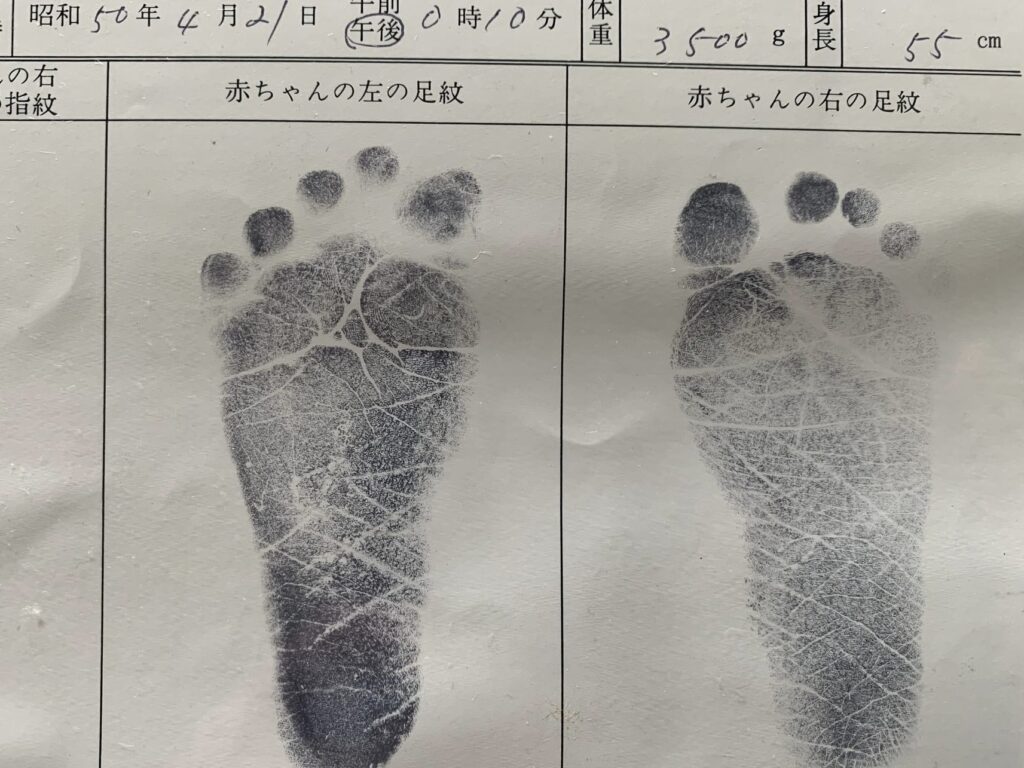
これまでの葛藤や苦悩や失敗が、自分と向き合うきっかけをくれ、そして自分のリカバリー材料になってくれた。
毎日を途方に暮れて過ごしていた昔の私に、今の自分の姿は想像もできなかっただろう。
「どんな時でもピンチはチャンス」そう思えるようになった私。
人生は旅だ。
何が起こるか分からない。
だけど、想定外が楽しいのだ。
だって、それはまた新たな道を発見する光となるから。

人生はネタの宝庫。
欠陥は、自分を見直しリカバリーするための強み。
不安は変化の兆候。
失敗は笑いに変わる。
何にでも、自分の味方につけられるし、強みにできるのだ。
今の私は、今日も自分に微調整をかけながら人生を旅している。

生きづらさを感じる人が一人減れば、その周りの人たちの環境も変わる。
怒りや憎しみが連鎖するように、笑顔も連鎖する。
この社会に、笑顔の連鎖を作っていく一片になれるよう、そうなりたいと願って、私は今日もカウンセリングを続けている。


